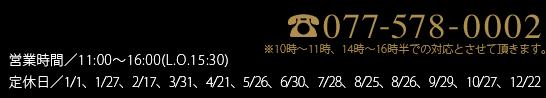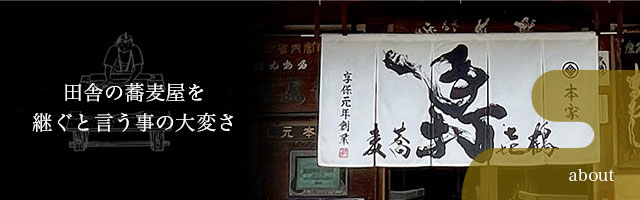六代目喜八郎の一人娘の静には長男の多万喜と次男の安正がいた。安正は祖父である六代目の喜八郎に可愛がられ、幼少期から坂本四丁目の鶴喜そばで「手打ち坂本そば」を教え込まれた。六代目の時には店の池には鯉、庭に鶏小屋、そして製粉所も持ち、住込みの従業員が作ってくれる三度の食事も自給自足である程度事足りたため、全ての給料は延暦寺の不滅の法灯の油に捧げていた。六代目は延暦寺まで上る際、幼い八代目安正が「草履の中に石が入って痛くて延暦寺の山に登るのはもう嫌だ」と泣いても八代目の修業として毎回付き添わせ過酷な山を上らせていた。八代目は後に東京で住込みで働き、品川店や皇居の敷地内の店舗で勉強し、昭和天皇へお出しする際の手打ちの蕎麦も六代目は八代目に付き添わせた。そんな自信がついた八代目安正にどうしても結婚したい節子の存在が出来、伝えるも「蕎麦屋には立ちたくない」と断られ自信喪失。「俺は次男だから絶対に蕎麦屋を継ぐ事は無いから勿論店に立たなくていい」と何度も説得しやっと結婚してもらえた。しかし長男の上延多万喜が吉兆創業者の湯木貞一に見込まれ、二女の準子さんと結婚し事態は急展開。急遽、次男の安正が店を継ぐ事となった。節子には「結婚時の約束と全く違ってくるが、こうなったら店の若女将になってしまうわけで、どうか店に立ってはもらえないか」と節子を説得。説得に説得で泣く泣く受け入れてくれた節子の生活が一変した。店には大女将がいた。まずは一番下の段の土間での生活が始まった。今まで自由に使えていたお財布を持てなくなった。店の材料を買いに行く時だけお金を持たされた。そんな毎日が続いたと大人になってから親に聞かされた。
しかし九代目の自分の時は、と言うと彼女に「田舎の蕎麦屋には立ちたくない」と言われたまま何の覚悟も無く結婚してしまった。しかし、そろそろ九代目の俺も店を継ぐ時が来る。妻にもやはり籍を入れた以上はどうか店に立ってはもらえないかとお願いしたが「田舎の蕎麦屋には立ちたくない」と、また同じ答えが返ってきた。彼女は全く別の仕事へと突き進んで行った。自分の父が成し遂げたように奥さんを説得する事は自分には出来ず、そのまま彼女は亡くなってしまった。彼女が亡くなってしまったからこそ本気で思えた事で「どうか十代目の時には奥さんの方からどうかこの店で是非働かせて欲しい」と言ってもらえる蕎麦屋にしたい、と覚悟が出来た。自分の本気が始まった。「ならば、田舎だからこそ坂本にある素晴らしい物を探していきましょう」そう言って下さる方との出会いも出来、15年がたった今、昔とは全く違う店となり「田舎の蕎麦屋」の悪いイメージだけはその方達のお陰で変えてもらえた事に感謝しています。
八代目は亡くなる際、店を頼む、と店のために言いたくない事を沢山言って逝ってくれた。自分九代目と亡くなった妻が八代目夫婦に多大な迷惑をかけていた事を初めて面と向かって言ってきた。人生初めて怒られた。自分が死ぬ前に気付く事が出来有り難う、と感謝した。今から自分の中で店への恩返し、坂本と言う地域への恩返しをしようと言う気持ちになれたからだ。親はその言葉私にとても言い辛かったと思う。亡くなっていく前に私に気付け、と本気で最後向き合ってくれた。何をしていいか分からないならとりあえず「現場に立て、お客様の声を聞け」、とにかくお客様がヒントを持っている。こんな事も八代目の口から聞くことが出来て本当に良かった。坂本の目の前向かいで頑張っている穴太衆の方達の「石の声を聞け、人生死ぬまで修業」が浮かんでくる。八代目は亡くなる最後も「ここまで職人技で何百年も繋いできたんだ、死んでも機械打ちにするなよ」と言い残していった。そう、田舎の人手不足なこの地で今後どんなに職人が足りなくなっても手打をやめてはいけない、その事を次の代までちゃんと面と向かって口伝で繋いでいけ、と。その時また更なる覚悟が決まった。
九代目 上延昌洋